「左利きの日なんかあるの?それっていつなの?」と疑問に思った方へ。
この記事では、8月13日の国際左利きの日と、2月10日の日本独自の左利きグッズの日という、年に2回ある「左利きの日」について詳しく紹介します。
それぞれの由来や制定の理由、なぜ左利きの日が2回あるのかという背景にも触れながら、左利きの歴史や右利きとの違いにも目を向けていきます。
また、左利きの日に開催されるイベントの事例や、韓国での認知状況、さらには左利きの芸能人によるエピソードも取り上げ、理解を深めるきっかけとなる情報を幅広くお届けします。
右利きが多数派である社会の中で、左利きの人がどのような体験をしているのかを知ることは、誰にとっても意味のある一歩となるでしょう。
・国際左利きの日と日本の記念日の由来と背景
・左利きの日に関連するイベントや事例
・左利きに関する社会的な課題とビジネスの可能性
左利きの日っていつ?2つの記念日を解説

-
左利きの日は8月13日と2月10日
-
国際左利きの日の由来と理由
-
なぜ左利きの日は2回あるのか
-
日本で定着した背景
-
左利きの日は韓国にもある?
-
右利きの日はいつ?存在するのか
左利きの日は8月13日と2月10日
左利きの人にとって、年に2回「自分たちに関係する記念日」があるのをご存知でしょうか。
1つは8月13日の「国際左利きの日」、もう1つは2月10日の「左利きグッズの日」です。どちらも、左利きの人々の暮らしやすさを考える上で意味のある日となっています。
まず、8月13日は1992年にイギリスの団体「Left-Handers Club」によって制定されたもので、国際的に認知されています。
この日は左利きの人々が日常生活で感じている不便さを可視化し、メーカーや社会に対して道具や環境の改善を訴える機会とされています。
例えば、右利き前提で設計されている改札機や自動販売機の不便さ、横書きノートでの書きづらさなどが挙げられます。
一方の2月10日は、日本独自の記念日として制定されました。語呂合わせの「0(レ)2(フ)10(ト)」が由来で、2001年に「Japan Southpaw Club」が初めに「左利きの日」として提案しました。
その後、2009年に「左利きグッズの日」と改称され、左利き向け商品を取り扱う企業によって日本記念日協会に正式登録されています。
このように、2つの日付はいずれも左利きの人々への理解や配慮を促す貴重なきっかけです。さらに、企業がこの日を活用してキャンペーンを行ったり、SNSで左利きにまつわる話題を発信することで、多くの人々に関心を持ってもらうことが可能になります。
ビジネス的な観点からも、年に2回ある「左利きの日」はプロモーションのチャンスとして注目されています。
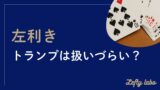
国際左利きの日の由来と理由
国際左利きの日(International Left-Handers Day)は、1992年にイギリスの「Left-Handers Club」が制定した記念日です。
毎年8月13日に実施され、左利きの人が抱える社会的・生活的な不便さへの理解を広め、左利き向け商品やサービスの開発を促す目的があります。
この記念日が8月13日に定められた背景には、Left-Handers Clubの提唱者の誕生日にちなんでいるという説があります。
ただし、正式な公的根拠は明示されていません。それでも、多くの国や地域でこの日が広く受け入れられており、現在では「左利きの権利を考える日」として国際的な認知が進んでいます。
Left-Handers Clubは、左利き用の文房具や台所用品を販売する英国の専門店「Anything Left-Handed」の運営団体が母体となっています。この団体は、左利きの生活環境を向上させることを使命としており、教育現場での理解促進、製品開発、社会的啓発など幅広い活動を行っています。
国際左利きの日には、世界各国で左利きに関するイベントや情報発信が行われます。例えば、SNS上で左利きに関する「あるある」体験がシェアされたり、左利き用の商品を紹介するキャンペーンが展開されたりします。
また、企業や自治体がこの日に合わせてプレスリリースを配信するケースもあり、メディアに取り上げられることもあります。
つまり、この記念日は単なる「記念日」にとどまらず、左利きの人の声を社会に届けるための重要な起点になっているのです。
なぜ左利きの日は2回あるのか

左利きの日が年に2回ある理由は、国際的な記念日と日本独自の事情が組み合わさっているからです。この構造を理解すると、日本での記念日運用の柔軟性や文化的な違いについても見えてきます。
まず、国際左利きの日(8月13日)は、イギリスの団体によって世界に向けて発信された記念日です。
この日を中心に、左利きが直面する課題や製品改善の必要性について議論が広がります。しかし、日本ではこの日が「お盆休み」の時期と重なるため、企業や教育機関がイベントを実施しづらいという問題がありました。

これを補う形で登場したのが、2月10日の「左利きグッズの日」です。この日は、日本独自の語呂合わせ「0(レ)2(フ)10(ト)」に基づいて制定されました。
記念日としても、日本記念日協会に登録されており、左利きグッズの販促や啓発活動の起点として定着しつつあります。
ここで注目すべきなのは、2つの記念日が目的を共有しながらも役割を分担している点です。国際左利きの日はグローバルな意識向上のために機能し、左利きグッズの日は日本国内での商業的・啓発的活動に適した日として活用されています。
もちろん、複数の記念日があることで混乱を招く可能性もあります。しかし、その一方で、広報活動や商品プロモーションのチャンスが年に2回あると考えれば、マーケティング上のメリットも大きいといえるでしょう。
このように、左利きの日が2回存在するのは、国際的な啓発と国内事情への対応という、双方のニーズを満たすための柔軟なアプローチなのです。
日本で定着した背景
日本で「左利きの日」が定着した背景には、文化的な事情と企業による積極的な情報発信が密接に関係しています。
世界的には8月13日が国際的な左利きの日として知られていますが、日本ではこの日がお盆の時期と重なってしまうため、記念日としての活動が難しいという現実がありました。
多くの企業やメディアが休暇に入るため、広報やイベントの実施がタイミング的に合わないのです。
このような事情を踏まえて、日本では2月10日が「左利きグッズの日」として独自に制定されました。この記念日は「0(レ)2(フ)10(ト)」という語呂合わせに由来し、記念日の制定は2001年に「Japan Southpaw Club」によって行われました。
さらに、2009年には神奈川県にある左利きグッズの専門商社「菊屋浦上商事株式会社」により、記念日協会への登録も済まされています。
こうした経緯により、日本では「左利きグッズの日」を軸にしたマーケティングや啓発活動が行いやすくなりました。
特に「左ききの道具店」などの専門店がこの日を活用して期間限定のキャンペーンやポップアップストアを開催し、消費者の関心を引き付けるきっかけを作っています。
また、左利きというテーマは「個性」や「多様性」といった現代的な価値観と相性がよく、SNSなどのメディアでも広く共感を集めやすい要素です。このため、企業やメディアが自主的に「左利きの日」を取り上げる機会が増え、結果として日本国内でも一定の認知が定着してきたと言えます。
左利きの日は韓国にもある?

韓国において、「左利きの日」として公式に制定された日は現在のところ存在していません。ただし、国際左利きの日である8月13日は、韓国でも一定の認知を得ています。特に若年層や教育関係者の間では、SNSやメディアを通じてこの記念日を知る人が徐々に増えているようです。
韓国では教育制度や社会慣習において、かつては日本と同様に「右利きへの矯正」が行われていた歴史があります。
特に1960〜80年代には、学校教育で左手での筆記や食事が否定的に扱われることがありました。そのため、現在でも左利きであることに対して少なからず不便さやプレッシャーを感じる人がいるのが現状です。
一方、最近では左利きに対する見方も徐々に変わってきており、教育や育児の場面では「本人の自然な利き手を尊重する」という姿勢が少しずつ浸透しつつあります。
また、韓国でも文具やキッチン用品の一部に左利き用の商品が並ぶようになっており、消費者のニーズに対応する姿勢が見受けられます。
とはいえ、企業が主体的に「左利きの日」に合わせた販促やイベントを実施している例はまだ多くありません。現状では国際的な記念日を情報として紹介するにとどまり、社会的なムーブメントとして広がっているとは言いがたい状況です。
このように、韓国では左利きの日が制度的に整備されているわけではないものの、グローバル化や価値観の変化により、今後徐々に注目が集まる可能性はあります。
右利きの日はいつ?存在するのか
「左利きの日」に対して、「右利きの日は存在するのか?」と疑問を持つ人も少なくありません。結論から言えば、正式に認定された「右利きの日」は現時点では存在していません。
これは、右利きが人類の大多数を占めており、社会制度や道具が右利き前提で作られていることが理由のひとつと考えられます。
現在、世界の人口の約9割は右利きとされており、多くの製品や施設は自然と右手での使用を前提とした設計になっています。
例えば、自動改札機のタッチ位置、はさみの刃の合わせ方、キッチンツールの形状などがそれにあたります。このような環境の中では、右利きの人は特別な支援を必要としないため、記念日として注目される機会が少ないのです。
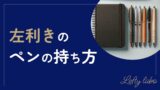
ただし、右利きの人に対しても利き手に関する啓発が無意味というわけではありません。むしろ、左利きと右利きの違いや、脳の働き・身体の使い方のバリエーションについて理解を深めるきっかけとして、「利き手」をテーマにした教育やイベントは価値があります。
また、今後は「左右の利き手に配慮した製品設計」や「誰もが使いやすいユニバーサルデザイン」の観点から、右利きであっても改めて自分の利き手について考えるきっかけが求められるかもしれません。
そういった動きの中で、「右利きの日」が新たに誕生する可能性もゼロではないでしょう。
つまり、現段階では公式な「右利きの日」は存在していないものの、利き手にまつわる多様な視点を社会に届ける機会として、将来的には制定の機運が高まる可能性もあります。
左利きの日をもっと知るためのトピック

-
左利きの歴史と社会での変化
-
左利きの日に開かれるイベント例
-
左利きの芸能人が語るエピソードとは
-
左利きの人が抱える日常の不便
-
左利きをビジネスに活かす視点
-
左利きの日をPRに活用する方法
左利きの歴史と社会での変化
左利きに対する社会の見方は、時代とともに大きく変わってきました。古代から近代にかけて、左利きはしばしば「異質」な存在として扱われ、時には否定的な意味合いで捉えられることもありました。
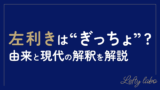
多くの文化圏では右手が「正しい手」とされ、左手は不吉、不浄といったイメージと結びつけられていたのです。
例えば、中世ヨーロッパでは「右=正義・神聖」「左=悪・不吉」といった価値観が広く浸透しており、左手で十字を切ることはタブーとされていました。
また、日本でも古くから筆記や食事の作法において右手を使うのが当たり前とされていたため、左利きの子どもが学校や家庭で「右手に矯正される」ことが珍しくありませんでした。
しかし、20世紀後半から現代にかけて、左利きへの理解と受容は徐々に進んでいます。特に1970年代以降、脳科学や教育心理学の研究が進む中で、「利き手は個性の一つであり、無理に矯正すべきではない」との考えが広まりました。
これにより、教育現場や子育ての方針にも変化が生まれ、自然な利き手を尊重する風潮が広がっています。
現在では、左利き専用の文房具やキッチン用品、スポーツ用品などが市販され、日常生活の不便を軽減する商品が増加しました。
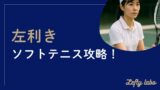
加えて、左利きが珍しさや話題性として注目されることもあり、SNSやメディアを通じて左利きの「あるある」体験が共感を呼ぶようになっています。
このように、かつてはマイナスイメージを持たれていた左利きも、今では多様性の一つとして受け入れられる社会へと変わりつつあります。
左利きの日に開かれるイベント例
左利きの日には、左利きの人々への理解を深めるためのさまざまなイベントが各地で開催されています。特に注目されているのは、企業や専門店が主催する体験型の催しやキャンペーンです。
たとえば、日本国内では「左ききの道具店」が毎年2月10日前後に開催する「おでかけストア」というポップアップイベントが人気を集めています。
このイベントでは、左利き用のハサミや文具、キッチンツールなどを100点以上展示・販売し、来場者が実際に手に取って試せるようになっています。
また、オンラインショップでも記念日にあわせた割引キャンペーンやノベルティ配布が行われ、遠方のユーザーも参加しやすい仕組みが整えられています。
海外に目を向けると、国際左利きの日(8月13日)にはイギリスやアメリカを中心に、左利きに関する啓発ポスターの掲示、学校での特別授業、左利き用商品の展示販売などが行われるケースもあります。
中には、右利きの人が左手だけで過ごす「左手チャレンジ」イベントを実施し、日常の不便さを体験する企画も存在します。
こうしたイベントは、単なる販売促進ではなく、左利きという特性を正しく理解してもらう教育的な意義も持ちます。特に子どもを持つ家庭や教育関係者にとっては、左利きの個性をどう受け入れ、どう伸ばすかを考える良い機会となるでしょう。
なお、参加者にとってもイベントは「自分だけじゃない」と感じられる安心感や連帯感を得られる場でもあります。左利きという共通点で集まることで、普段はなかなか語り合えない悩みや工夫を共有するきっかけにもなるのです。
左利きの芸能人が語るエピソードとは
芸能界には多くの左利きの人物が存在し、メディアやインタビューで自身の体験を語ることもあります。彼らの話からは、左利きとして生きる上での工夫や苦労、そして意外なメリットが垣間見えます。
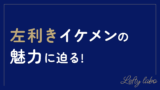
例えば、人気俳優やアーティストの中には、学校時代に「左利きだから目立った」「字が汚いと注意された」などの経験を語る人もいます。特に書道や家庭科の授業など、右手前提で進行するカリキュラムでは不便さを感じることが多かったとされています。
しかし一方で、「ギターの弾き方がユニークで褒められた」「他の人と違うからこそ覚えてもらいやすかった」といったポジティブな面を話す人も少なくありません。

また、バラエティ番組では「左利き芸能人あるある」企画が組まれることもあり、左利きならではの困りごとが笑いを交えて紹介されます。
代表的なエピソードとして、「横書きのサインを書くと手がインクで真っ黒になる」「テーブルで隣の右利きと腕がぶつかる」などが挙げられます。これらの話題は、視聴者にとっても共感や気づきを生む内容となっています。
また、料理番組やドラマ撮影の現場でも、左利きであることが話題になるケースがあります。
調理器具の配置や、演技の動線に関して右利き仕様が当たり前であるため、少し戸惑うこともあるようです。しかし、こうした苦労も経験値として語られることで、視聴者に左利きへの理解が広まるきっかけになります。

このように、芸能人が自身の左利きに関する体験をオープンに語ることで、左利きに対する偏見や誤解が和らぎ、社会全体での受容にもつながっています。
個性を活かしながら活躍する姿は、左利きの子どもや保護者にとっても心強いロールモデルとなるでしょう。
左利きの人が抱える日常の不便

左利きの人が生活の中で直面する「小さな不便」は、右利きが大多数を占める社会では見落とされがちです。
道具や設備の多くが右利き基準で作られているため、左利きの人にとっては工夫や我慢が必要な場面が日常的に存在します。
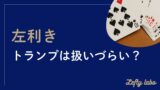
代表的な例として、文房具やキッチン用品があります。例えばハサミは、刃の重なりが右利き用に設計されているため、左手で使うと刃先の接点が見えにくく、正確に切ることが難しくなります。
また、ボールペンやマーカーで文字を書く際、左手が書いた直後のインクの上をこすってしまい、手が汚れたり文字がにじんだりすることも珍しくありません。
公共の設備でも、改札機やエレベーターのボタン、自動販売機のコイン投入口などは右手の使用が前提とされています。これにより、左利きの人は身体をひねるような不自然な動作を強いられることがあり、日々のストレスに繋がっています。

さらに、教育や職場でも無意識に右利き前提の環境が形成されています。黒板に書く方向や席の配置、書類の綴じ方など、右利きにとっては当然でも、左利きにとっては非効率に感じることもあるでしょう。
このような日常の不便は、直接的なトラブルにならなくても、少しずつ蓄積されて精神的な負担となる場合があります。特に子どもにとっては、周囲との違いに悩んだり、必要以上に矯正される経験がストレスの原因になることもあります。
しかし、近年では左利き用の商品が増え、ユニバーサルデザインの導入も進んでいます。それでも、社会全体の理解と工夫がなければ、不便の完全な解消には至りません。こうした視点を持つことが、誰にとっても使いやすい社会をつくる第一歩になります。
左利きをビジネスに活かす視点
左利きの人は世界人口のおよそ10%とされており、少数派であるがゆえにビジネス面では独自の需要とニッチ市場の可能性を秘めています。これを機会としてとらえれば、他社と差別化できる商品開発やマーケティング戦略が見えてきます。
まず、左利き専用の商品は「困りごとに対する明確な解決策」を提供することができるため、共感と満足度の高い購買体験を提供できます。たとえば、左利き用の文具、調理器具、美容ツールなどは、使い勝手の良さから口コミで広がりやすく、リピート購入に繋がる傾向も強いです。
また、左利き向けの商品はその希少性から「ギフト需要」や「話題性」にも強く反応します。バリエーションの少なさを逆手に取り、デザイン性やカラーバリエーションを強化することで、左利きユーザーに「選ぶ楽しさ」を提供できるのです。こうした視点は、購買意欲を刺激するだけでなく、ブランドへの愛着形成にも効果的です。
さらに、左利きの特性はマーケティング面でも活用できます。SNSキャンペーンやプロモーションにおいて、「左利きあるある」や「左利きだからこその工夫」などをコンテンツにすれば、共感を呼びやすく、自然な拡散が期待できます。実際に大手文具メーカーが左利き向けボールペンを発売した事例では、使用者の声をもとに開発したことが話題を呼び、販売数を大きく伸ばしました。
一方で、左利きのニーズに応えるには、製造や在庫管理などの面でコストがかかる場合もあります。また、市場規模が限定されるため、大量生産には向いていないことも事前に考慮する必要があります。
とはいえ、こうした少数派の声にしっかり向き合う企業姿勢は、顧客の信頼を得る大きな資産になります。多様性を重んじる現代において、「左利き」をビジネスチャンスとして捉える視点は、今後ますます重要性を増すでしょう。
左利きの日をPRに活用する方法
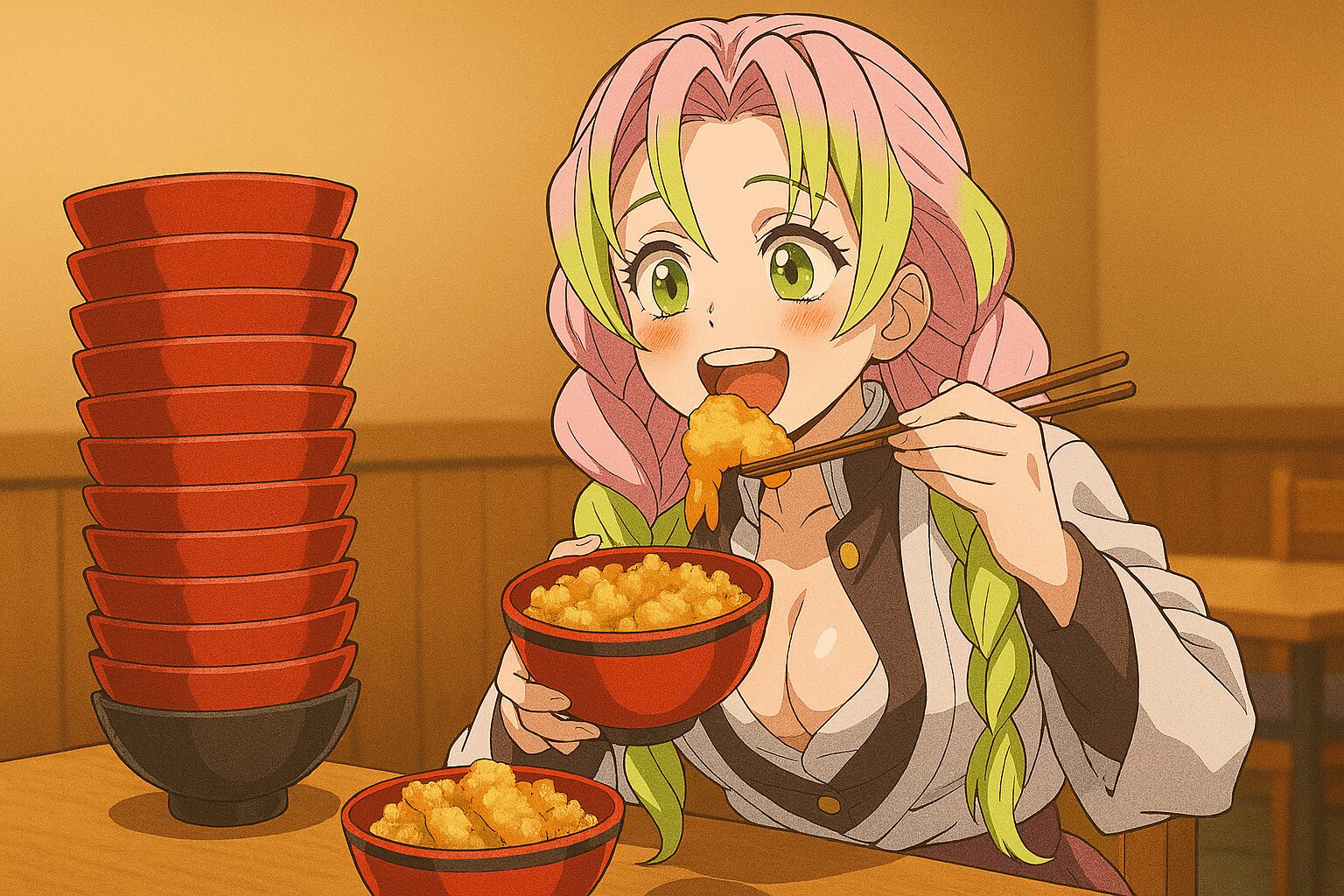
鬼滅の刃の甘露寺蜜璃ちゃんも実は左利き説??
(筆者イメージイラスト)
「左利きの日」は、企業やブランドがユニークな視点で注目されるための格好のPRチャンスです。
特に、商品やサービスに「利き手の違い」が関わる場合、8月13日(国際左利きの日)や2月10日(左利きグッズの日)を活用することで、話題性と共感性のある情報発信が可能になります。
活用の第一歩として有効なのが、プレスリリースやSNSを通じた自社取り組みの紹介です。
たとえば、左利き向けに開発した商品や、新しいキャンペーンを「左利きの日」に合わせて発信すれば、メディアや消費者の目を引きやすくなります。近年では、左利きの社員が語る開発エピソードを交えたリリースも注目を集めやすい形となっています。
また、左利きに関する「意識調査」や「困りごとエピソード」をコンテンツ化するのも効果的です。企業ブログや特設ページで左利きの課題やユニークな体験を共有することで、右利きのユーザーにも興味を持ってもらえる可能性が高まります。
さらに、イベント型の施策もPRとして有効です。左利き体験コーナーを設置したポップアップストアや、左利き限定キャンペーンなど、実際に「不便さ」と「工夫」を体験できる企画は、来場者とのコミュニケーションにも繋がります。
ただし、発信する際には「マイノリティであることを強調しすぎない」「左利き=不便という先入観を助長しない」など、表現には注意が必要です。左利きの存在を「不便さ」ではなく「個性や多様性」として捉え、前向きなメッセージを発信することが求められます。
このように、「左利きの日」は商品やブランドの価値を伝えるだけでなく、社会的な配慮や共感を示す絶好の機会です。単なる販促にとどまらず、ブランドの信頼性や社会性を高めるための手段として戦略的に活用していくことが重要です。
左利きの日は年に2回!深く知るためのポイント
最後に、本記事をまとめていきます。左利きにとって歓喜の日は年に2回あります。私も徹底調査して初めて知った面もあります。左利きコミュニティがさらに盛り上がるのを期待していきたいですね。
- 8月13日は国際左利きの日で1992年に英国で制定
- 2月10日は日本独自の左利きグッズの日
- 2月10は0‑2‑10の語呂合わせで生まれた
- 国際左利きの日は左利きの不便を可視化する目的
- 左利きグッズの日は販促と啓発に特化する
- 日本で8月13日が浸透しにくい理由はお盆休み
- Left‑Handers Clubが国際デーを主導する団体
- 菊屋浦上商事が日本記念日協会へ登録済み
- 右利きの日は公式に存在しない
- 韓国には公式の左利きの日はまだない
- 左利きの歴史は差別から多様性尊重へ転換
- 左利き向け商品が文具から家電まで拡大
- イベント例としてポップアップや左手チャレンジがある
- 企業は左利きの日をPR施策の好機と捉える
- 左利き市場は10%のニッチながら高い需要がある


