左利きで編み物をする際に、もしかすると「左利きだと編み物はできない」と言われた経験があったり、「やっぱり難しい?」と感じているかもしれません。
実際、編み物に関する情報や教材の多くは右利き向けに作られているため、左利きの方にとっては最初の一歩がやや高く感じられることがあります。
しかし、左利きでもできるかぎ針編みの作り目や、左手で行うかぎ針・クロッシェ編み、棒針編みなど、正しい情報とコツを押さえれば、誰でも編み物を楽しむことができます。最近では左利き用の本や動画、教室なども充実しており、初心者でも安心してスタートできる環境が整いつつあります。
また、「編み方」そのものを覚えるだけでなく、脳に効果がある?という疑問や、老化防止になる?といった健康面での関心も高まっています。
本記事では、左利きで編み物を始める際のポイントや注意点、教材の選び方まで、役立つ情報をわかりやすくご紹介します。
左利きだからといって難しい、できないと諦める必要はありません。むしろ、あなたらしいスタイルで編み物を楽しめるチャンスです。
-
左利きでも編み物は問題なくできること
-
左利き向けの教材や練習方法があること
-
右利きとの違いや注意点が分かること
-
編み物の健康効果や楽しさを知ること
左利きだと編み物は本当に難しいの?

-
編み物はできないと言われるのは本当?
-
左利きでもできるかぎ針編みの作り目は?
-
かぎ針編み(クロッシェ編み)を左手で編むには
-
初心者が注意すべきこと
-
右利きの編み方との違い
-
編み物には脳にどのような効果があるか?
編み物はできないと言われるのは本当?
「左利きだと編み物はできない」と言われることがありますが、それは事実ではありません。左利きの方でも、工夫次第で問題なく編み物を楽しむことができます。
たしかに、世の中の編み物の教材や道具の多くは右利き用に作られています。そのため、最初は右手中心の操作や編み図の見方に戸惑うことがあるかもしれません。特に初心者のうちは、教室や動画の説明がすべて右利き前提になっていると、混乱しやすいです。
しかし、左利きに対応した本や動画も近年では増えており、左手での編み方を解説する専門書や専用の編み図も手に入るようになりました。また、慣れてくれば編み図を頭の中で左右反転させて理解できるようになる方も多いです。
言ってしまえば、「左利きだからできない」のではなく、「左利き用の情報が少ないため、学び始めが少し複雑」というのが現状です。環境が整っていない部分はあるものの、技術として編めないわけではないのです。
このように、左利きであっても正しい知識とサポートがあれば、編み物は十分に可能な趣味となります。
左利きでもできるかぎ針編みの作り目は?

左利きの方でも、かぎ針編みの作り目をきちんと編むことができます。やり方さえ分かれば、右利きと変わらない仕上がりになります。
かぎ針編みにおける「作り目」とは、編み始めに鎖編み(くさりあみ)を編んでベースを作る工程のことです。このとき、左手でかぎ針を持つ場合は、右手で糸を操作することになります。つまり、利き手が逆になるだけで、基本的な構造や目の順番は変わりません。
注意点として、一般的な編み方の説明や図は右利き用に作られているため、目の進行方向や編み図の読み方を左右反転して理解する必要があります。最初は少し混乱しがちですが、動画などで動きを視覚的に覚えるとスムーズです。
例えば、左利き専用の教本やレッスン動画では、作り目の編み方を実際に左手で行う様子が紹介されているため、参考になります。また、鏡を使って右利き用の動きを左右逆に見ることで、練習しやすくなるという工夫もあります。
こうした工夫を取り入れれば、左利きでも違和感なく作り目をマスターすることができます。初めはゆっくりでも、自分のペースで慣れていくことが大切です。
かぎ針編み(クロッシェ編み)を左手で編むには
左手でかぎ針編み(クロッシェ編み)をする場合、基本的には右利きの手順を左右反転する形になりますが、独自のコツや注意点があります。
まず、左手で編むときは、かぎ針を左手で持ち、糸を右手でコントロールします。目の進行方向が右から左に変わるため、編み図をそのまま使用すると正しい形にならないことがあります。そのため、編み図の見方を左右反転させるスキルが必要です。
また、毛糸の撚り方向にも注意が必要です。多くの毛糸は右利きで編むことを前提とした「S撚り」のものが多く、左手で編むと撚りがほどけやすくなる傾向があります。これにより、編み目が少し緩く感じられることがありますが、慣れれば編み方で調整できるようになります。
もう一つのポイントは、参考にする教材の選び方です。左利き向けに撮影された動画や、作業工程が左右反転された本は、学習の助けになります。特に初心者の方には、視覚的に見て真似がしやすい動画教材がおすすめです。
このように、最初のハードルは少し高めですが、左手でクロッシェ編みをすることは十分に可能です。習得後は右利きの人にはできないアプローチもできるため、独自のスタイルで編み物を楽しむことができるでしょう。
初心者が注意すべきこと
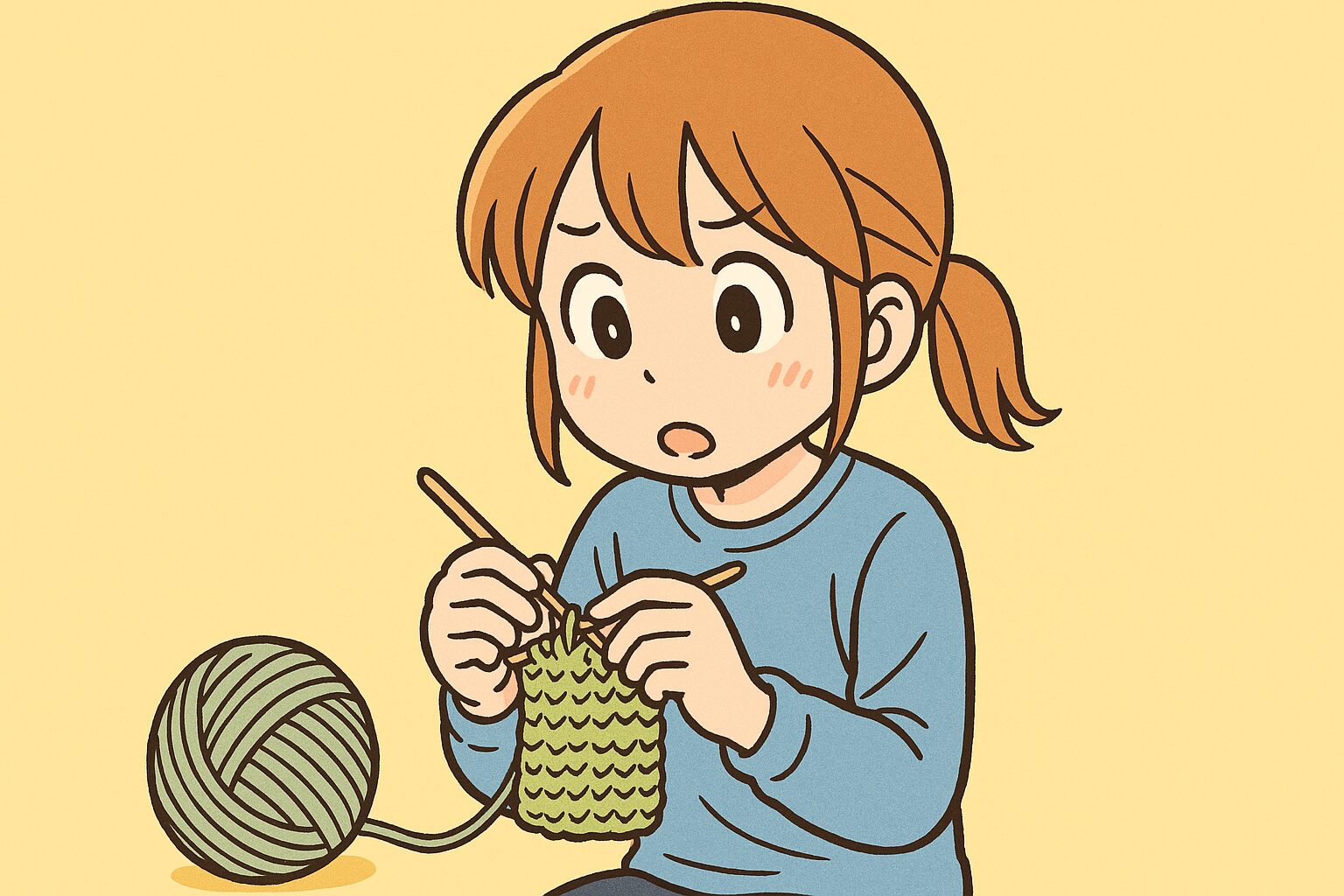
左利きの初心者が編み物を始める際には、いくつかの点に注意することでスムーズなスタートが切れます。特に、情報収集と練習の方法が重要です。
まず気をつけたいのが、教材の選び方です。市販されている多くの編み物の本や動画は右利き用です。左手で同じ動きをしようとすると混乱する可能性があるため、左利き向けに作られた教材や、左右反転して使える動画などを選びましょう。
次に、最初のうちは「右利き用を無理に真似しない」ことがポイントです。手の動きや持ち方を自己流にアレンジしてしまうと、後で直すのが大変になることもあります。正しいフォームを覚えるためには、動きを映像で確認しながら練習するのがおすすめです。
また、利き手に合わせて使う道具にも配慮が必要です。かぎ針の形状やグリップ感も手に合うものを選ぶことで、手の疲労を抑えやすくなります。
このように、初心者の段階では「正確な情報を選ぶ力」と「慣れるまでの反復練習」が成功の鍵となります。焦らず、楽しむ気持ちを大切にして始めてみましょう。
右利きの編み方との違い
左利きで編む場合、右利きの編み方とはいくつかの明確な違いがあります。特に「編む方向」「糸の撚り」「編み図の読み方」の3点が代表的です。
最も基本的な違いは、編み進める方向です。右利きは左から右へ針を動かしていくのに対し、左利きの場合は右から左に進めることになります。この違いにより、見本通りに仕上がっているように見えても、実際には左右対称の作品になってしまうことがあります。
また、毛糸の撚り方向にも影響があります。市販の毛糸は右利き用の「S撚り」が主流で、左利きで編むと撚りが逆方向にかかるため、糸がほどけやすくなったり、見た目が少し硬くなったりすることもあります。
さらに、編み図の読み方にも工夫が求められます。ほとんどの編み図は右利き用に作られているため、左利きで編む場合は左右反転して解釈しなければならないことが多いです。
これらの違いを知っておくだけでも、途中で戸惑う回数を減らすことができます。逆に言えば、左利きならではの方法を身につければ、自由な発想でオリジナル作品を生み出す力にもつながるでしょう。
編み物には脳にどのような効果があるか?

編み物には、集中力の向上やストレス軽減など、脳にさまざまな良い影響があるとされています。単なる手作業に見えるかもしれませんが、実際には多くの脳の領域が活性化しています。
編み物中は、手先を使いながら次に何目編むかを考えたり、模様のパターンを記憶したりといった作業が繰り返されます。これにより、前頭葉や海馬といった認知機能に関わる部分が自然と刺激されるのです。
また、単調でリズミカルな動作が続くことで、心拍が安定し、リラクゼーション効果が生まれることもわかっています。これは瞑想と似たメカニズムで、脳内にセロトニンが分泌され、気分が安定しやすくなるという報告もあります。
たとえば、高齢者が編み物を継続することで、認知機能の維持や軽度認知障害の予防につながったという例もあるほどです。若年層でも、日々のストレス解消や思考の整理に編み物を取り入れている人が増えています。
このように、編み物は単なる趣味を超えて、脳と心の健康を支える手段としても大きな効果が期待できます。日常に取り入れやすい「セルフケア」のひとつとして、非常に魅力的な習慣と言えるでしょう。
左利きでも編み物を楽しむための工夫

-
本を活用して学ぶ方法
-
編み物を学べる教室はある?
-
解説動画を探すコツ
-
左利きでも使える棒針の選び方
-
編み物は老化防止になる?
-
左利きで編み物をすることのメリットや楽しさとは
本を活用して学ぶ方法

左利きで編み物を始めたい場合、本を活用することは大きな助けになります。ただし、選ぶ本によっては右利き前提で書かれているものも多いため、内容を見極めることが大切です。
まず最初にチェックしたいのが「左利き対応」と明記されている本です。近年では、左利き専用のかぎ針編みや棒針編みの本が出版されており、写真や編み図がすべて左手仕様になっています。このような本を選べば、編み図を頭の中で反転させる必要がなく、スムーズに学べるようになります。
また、左利き対応ではなくても、見開きに動作の写真が連続して載っている本や、イラスト中心でプロセスを追いやすい構成になっているものも有効です。こういったビジュアル重視の本は、左手でどう動かせばよいかを自分なりに理解しやすくなります。
さらに、基本の動作を解説するページとあわせて、「Q&A」や「よくある失敗」のコーナーがある本は、つまずいたときのサポートとしても活躍します。多くは初級者向けにやさしく書かれているので、最初の一冊としておすすめです。
このように、自分のレベルや目的に合った本を選べば、独学でも十分に楽しく編み物を進めることができます。慣れてきたら右利き用の本を参考にすることも視野に入れると、さらに世界が広がるでしょう。
編み物を学べる教室はある?
左利きで編み物を学びたい場合、教室に通うことを考える方もいるでしょう。ただし、教室によっては右利き用の指導のみとなっているところもあるため、事前の確認が必要です。
まず探し方としては、「左利き歓迎」や「個別対応」と明記されている教室をインターネットで検索するのが効果的です。最近ではマンツーマンレッスンや小規模な手芸サロンが増えており、柔軟に対応してくれる講師も少なくありません。
また、大手カルチャーセンターの中には、左利きに理解のある講師が在籍している場合があります。問い合わせの際に「左利きでも大丈夫ですか?」と聞くことで、対応可否を事前に確認することができます。
どうしても左利きの直接指導が難しい場合でも、対面で右利きの動きを見ながら、自分の手で反転して真似していくという方法もあります。このようなケースでは、鏡を使って動きを左右逆に映すなど、工夫次第で理解が深まります。
一方で、グループレッスンだと個別に対応しきれない場合もあるため、最初は少人数制や個別指導の教室を選ぶと安心です。
このように、左利きでも学べる教室は確かに存在します。探し方と事前確認をしっかり行えば、自分に合ったスタイルで編み物を習得することが可能です。
解説動画を探すコツ

動画で編み物を学ぶ際、左利きの人にとっては「どの動画が自分向きか」を見極めることが重要になります。視覚的にわかりやすい一方で、右利き用ばかりだと混乱の元になることもあるためです。
まず最初のコツは、検索キーワードを工夫することです。「左利き かぎ針編み」「left-handed crochet」などの言葉を使って動画検索すると、左手で編んでいるクリエイターの動画が見つかりやすくなります。YouTubeでは特に、外国人の編み物チャンネルに左利き用のコンテンツが多く存在します。
また、動画のサムネイルや冒頭を確認し、「かぎ針を左手に持っているか」をチェックするのもポイントです。操作の向きや動きが自分の感覚と合っているかを確認することで、実際の練習時に混乱が少なくなります。
次に注目したいのは、スロー再生や繰り返し再生に対応しているかどうかです。細かい動きを何度も確認できる動画は、初心者が手順を覚えるのに非常に役立ちます。
さらに、字幕やナレーション付きの動画もおすすめです。手元だけでは分かりづらい意図や注意点が言葉で補足されるため、より深く理解することができます。
このように、動画を選ぶ際には「左手視点」「動きの分かりやすさ」「補足情報の有無」の3点に注目すると、スムーズに習得が進みやすくなります。環境を整えることで、動画学習は非常に強力な味方になります。
左利きでも使える棒針の選び方
左利きの方が棒針編みを始める際は、棒針自体の選び方にも気を配ると、より快適に編み進めることができます。特別な左利き用の棒針は存在しないものの、使いやすさを左右する要素はいくつかあります。
まず、針の素材に注目してみましょう。木製や竹製の針は滑りにくく、目が抜けにくいため、慣れないうちは扱いやすい傾向があります。逆に金属製は滑りが良すぎて、コントロールが難しいと感じることがあるため、初心者の方は避けた方が無難です。
次に考えたいのが針の長さです。左利きの場合、右手で糸を支えるスタイルになるため、長すぎる針は取り回しが悪くなることがあります。最初は短めの針(25cm前後)を選ぶと、動きが安定しやすくなります。
そして、輪針の利用も選択肢に入れておくと便利です。輪針は左右対称に動かせるので、左利きの動作にもフィットしやすい設計です。小物からセーターのような大きな作品まで対応できるため、長く使える道具として重宝します。
このように、左利きの方でも特別な道具を揃える必要はなく、素材・長さ・タイプを工夫することで、快適な棒針編みを楽しむことができます。
編み物は老化防止になる?

編み物は、脳や身体に良い刺激を与える活動として、老化防止の観点からも注目されています。特に、高齢者の認知機能の維持や、生活の質を保つうえでの効果が期待されています。
編み物をする際には、手先を細かく動かす必要があり、同時に頭の中では模様や段数、パターンなどを記憶・管理する作業が続きます。この「手と脳を同時に使う」という行動が、脳の活性化につながるのです。
たとえば、作品づくりでは計画性や集中力が求められます。新しい編み方を覚えるには記憶力も必要です。このような複合的な脳の使い方は、単純な頭の体操よりも効果的だといわれています。
また、リズミカルな手の動きにはリラックス効果があり、自律神経を整える働きも期待できます。心が落ち着くことで、睡眠の質が上がったり、日常のストレスが軽減されたりする例もあります。
これらの作用が重なり合い、結果として「老化予防」に良い影響を与えると考えられています。編み物は単なる趣味を超えて、心身の健康を支える手段としても価値のあるアクティビティといえるでしょう。
左利きで編み物をすることのメリットや楽しさとは

左利きで編み物をするのは不便だと思われがちですが、実は独自のメリットや楽しみ方も多く存在します。左利きならではの視点を生かせば、編み物はもっと自由で個性的な趣味になります。
第一に挙げられるのは、独自の表現ができる点です。左手で編むことで、自然と左右反転した編み地になる場合があり、これが結果として他の人と違うデザインの雰囲気を生み出すことがあります。既存のパターンにとらわれず、自分だけのアレンジを加えやすいのは大きな魅力です。
また、左利きで編めるようになると、右利きの人にも教えることが可能になります。両方の立場を経験することで、教え方の幅が広がり、将来的に講師や手芸活動に活かせるという利点もあります。
さらに、自分に合った動作や持ち方を工夫するうちに、自然と観察力や問題解決力が身につくのもメリットです。たとえば、右利き用の動画を見ながら左右逆に動きを読み取る練習を続けることで、理解力や応用力が高まります。
このように、左利きで編み物をすることには確かに工夫が必要ですが、その分だけ自分らしさや学びが深まる楽しさがあります。技術の習得を超えて、新しい視点や可能性を発見できるのも、編み物の魅力の一つといえるでしょう。
左利きさんの編み物の始め方と楽しみ方まとめ
最後に、左利きの方の編み物についての本記事をまとめます。
-
左利きでも編み物は可能であり、「できない」は誤解にすぎない
-
作り目や基本動作は左手でも習得可能。左右反転を意識することがポイント
-
クロッシェ編み(かぎ針編み)を左手で行うには、編み図や手順の反転が必要
-
初心者は右利き用教材を無理に真似せず、左利き対応の本や動画を活用するのが安心
-
右利きとの主な違いは「編む方向」「糸の撚り」「編み図の見方」など
-
編み物は脳を活性化させ、集中力や記憶力を高める効果も期待できる
-
左利き対応の本は、視覚的に理解しやすく練習にも最適
-
教室を探す際は「左利き対応」かどうかを事前に確認することが大切
-
解説動画は「左利き 編み物」などのキーワードで検索し、視点や再生機能に注目
-
棒針は素材や長さ、輪針の活用などで左利きでも扱いやすくなる
-
編み物は老化防止やストレス軽減にも役立つ、心と体に優しい趣味
-
左利きだからこそ生まれる独自のアレンジや表現が、編み物をより楽しいものにしてくれる
他に読まれている記事です。


