左利きの子供にピアノを習わせたい、またはご自身でもこれから始めたいという方の中には、ピアノの演奏時に不利にならないか、有利な面はあるのかと不安を感じている方もいるかもしれません。
実際、ピアノは右手主体の構成が多く、教本や指導法も右利きを前提に作られていることが少なくありません。そのため、左利きであることに対して「ハンディがあるのでは」と考えてしまうのは自然なことです。
しかし、左利きには左手の操作に長けているという強みがあり、曲によってはむしろ有利に働くこともあります。
とくに左利き向けのピアノ曲や、左右の役割が均等な楽曲では、その特性が大きく活かされます。また、「ピアノは右手と左手どっちが難しいのか?」という疑問についても、演奏内容や曲によって異なるため、単純な比較では判断できません。
このような左利きの個性は、ピアニカやバイオリンなどの他の楽器と比較しても、ピアノのほうが順応しやすい傾向にあります。
さらに、4歳でピアノを始めると、左右の手をバランスよく育てることができ、将来的に両利きに近い動きが身につくケースもあります。
音楽の聞こえ方に関しても、左右の脳の使い方の違いがあるとされ、左利きならではの感受性が演奏に活かされることもあるでしょう。
実際、坂本龍一さんなど左利きのピアニストで有名な人も多数存在しており、左利きが不利になるどころか、音楽的な個性や深みを生み出す要素にもなり得ます。「左利きの欠点は何か」と不安に思う前に、その特性をどう活かすかを考えることが大切です。
本記事では、左利きでピアノを学ぶ際の不安や疑問に対し、実態や最新の指導法をもとに丁寧に解説していきます。ピアノの才能がある人の特徴や、左利きの子が音楽の世界でどのように育っていくかについても触れながら、あなたやお子さんが音楽を自由に楽しめるヒントをお届けします。
-
左利きがピアノ演奏で不利かどうかの実態
-
左利きの特性を活かせる練習法や曲の選び方
-
ピアノと他の楽器(バイオリン・ピアニカ)との違い
-
左利きでも活躍するピアニストの存在と成功例
左利きのピアノは不利?有利?その実態

-
左利きの欠点は何があるのか
-
ピアノは右手と左手どっちが難しい?
-
左利きでもピアノは不利ではない理由
-
むしろ有利な面も
-
両利きの子はピアノでどう育つ?
-
左利きのピアニストで有名な人
左利きの欠点は何があるのか
左利きには個性や創造性の高さが注目される一方で、日常生活において不便さや不自由さを感じやすい場面も少なくありません。特に右利き用に設計された社会の中では、その影響を強く受けやすい傾向があります。

たとえば、文房具や調理器具の多くは右利き前提で作られており、左利きの人にとっては使いにくいものが多いです。
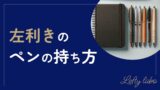
左手でハサミを使うと刃の向きが合わず、紙が切りにくくなったり、ボールペンのインクが手についてしまったりすることはよくある話です。

また、学校教育や習い事でも、教師が右手中心で説明することが多いため、無意識のうちに「やりづらさ」を感じる子どももいるでしょう。
音楽の世界でも、基本的に右手主体の動きが多く求められるため、左利きの人がその流れに合わせるには慣れが必要です。ピアノやバイオリン、ギターといった楽器において、教則本や演奏指導は右利きの前提で作られていることがほとんどです。
そのため、練習の初期段階で戸惑う人も少なくありません。
さらに、左利きの人は道具だけでなく、「周囲とのずれ」も感じやすいことがあります。たとえば食事の際、右利きの人の隣に座ると肘がぶつかりやすく、気を遣ってしまうという声もよく聞きます。こういった社会的なストレスは、見えにくいながらも確実に存在しています。
このように、左利きには右利き社会で生活していくうえでのハンディが複数存在します。ただし、それを「欠点」と決めつけるのではなく、配慮や工夫で十分に乗り越えられることが多いのも事実です。
現代では左利き用の道具も増えてきており、理解が広まりつつあります。これを前向きに捉え、適切に対処することで、左利きの個性を活かすことができるはずです。
ピアノは右手と左手どっちが難しい?
ピアノ演奏において、「右手と左手のどちらが難しいのか?」という問いには、一概に答えを出すことが難しいほど奥深いテーマが含まれています。
なぜなら、難しさの感じ方は演奏する曲の構造や演奏者の利き手、そして技術レベルによって大きく変わるためです。
一般的に、ピアノの楽譜では右手がメロディーを、左手が伴奏を担当するケースが多くなっています。このため、メロディーラインの細やかな表現や音量のコントロールが求められる右手の方が、表現力の面では難易度が高いと考えられています。
特にクラシック曲やロマン派の作品では、右手に複雑なパッセージや高速のスケールが求められる場面も多く、右手主導で音楽を組み立てるスキルが必要になります。
一方、左手の難しさは「目立たないけれど非常に重要な役割」にあります。左手はベースラインやリズムの土台を作り出すため、ミスや不安定さがあると演奏全体が揺らいでしまいます。
また、和音の押さえや跳躍、重音のバランスなど、技術的にはかなり要求される場面も少なくありません。特にバッハやインベンションなど、両手が独立して動く曲では、左手も右手と同等の表現力が求められます。
つまり、「どちらが難しいか」は単純に片付けられないテーマです。右手は表現力と技術の見せ場として、左手は演奏の安定性と構成力の要として、それぞれに異なる難しさが存在します。したがって、ピアノを学ぶうえでは、どちらの手もバランスよく鍛えることが非常に大切です。
私自身もピアノにチャレンジしていたとき、右手で旋律を弾きながら左手のコードを整えることに苦労しました。動きの多い右手ばかりに意識が向いてしまい、左手が置き去りになる感覚があったのを今でも覚えています。このように、両手の役割と難易度を意識しながら練習することが、上達の近道になるのではないでしょうか。
左利きでもピアノは不利ではない理由

左利きだからといって、ピアノ演奏において不利になるわけではありません。多くの研究や教育現場の経験からも、左右のバランスを取る練習を続けることで、右利きと同じように演奏力を伸ばすことが可能であることがわかっています。
確かに、ピアノという楽器は構造的に右手でメロディーを弾くことが多く、教本も右利きを前提に作られている場合がほとんどです。
この点だけを見れば、左利きの人が最初に戸惑いやすいのは事実です。しかし、それが「不利」という結論には直結しません。むしろ、左手が器用であるという特性が、伴奏や低音部の表現においては大きなアドバンテージになることもあります。
実際、左利きのピアニストでも世界的に活躍している人物は数多く存在します。坂本龍一さんやラフマニノフなど、名だたる音楽家たちが左利きでありながら、非凡な演奏力を持ち世界中で評価されてきました。
彼らは、左利きだからこそのコントロール力や音の深みを音楽に生かすことに成功した例だと言えるでしょう。
また、近年では左利きの子どもに向けて、最初に左手から練習を始めるアプローチや、左右を平等に使うカリキュラムを導入する教室も増えています。
こうした指導法を活用すれば、左利きの特性を無理に変えることなく、自然に技術を伸ばしていくことが可能です。
いずれにしても、ピアノは両手を使う楽器です。左利きかどうかに関係なく、どちらの手にも技術や表現力が求められる以上、「利き手の違い」は成長過程のひとつの個性にすぎません。
焦らず、地道に練習を積み重ねることで、左利きの人でも十分に魅力的な演奏ができるようになります。大切なのは、自分の手に合った練習法を見つけて、長く楽しんでいくことではないでしょうか。
むしろ有利な面も
左利きがピアノ演奏において「不利」と捉えられがちですが、視点を変えれば「むしろ有利」と言える側面もあります。ピアノは両手を均等に使う楽器であり、利き手が左であることが独自の強みを生む場面があるのです。
まず、左手が得意なことで、伴奏や低音パートを力強く安定して弾くことができます。多くのピアノ曲では、左手がリズムやハーモニーの土台を担うため、演奏の安定感に直結します。右利きの人が左手の動きに苦戦するパッセージでも、左利きの人は比較的スムーズに対応できるというケースは珍しくありません。
また、曲によっては左手に複雑な動きや独立したメロディラインが与えられることがあります。バッハやシューマンの作品などでは、左右の手が同等に主張する構成が多く見られます。そうした場合、左利きの人は左手の細かい動きに慣れているため、より繊細な表現がしやすいという利点があります。
さらに、左利きの子どもが幼少期にピアノを始めると、左右のバランスが取れやすくなることも注目されています。早期に両手を使う経験を積むことで、非利き手である右手の器用さも自然と育ち、結果として両手を均等に使えるようになります。これにより、表現力の幅が広がり、音楽的な柔軟性が養われやすくなるのです。
このように考えると、「左利き=不利」という固定観念には疑問を持つべきかもしれません。むしろ、個性としての左利きは、演奏技術の面で強みを発揮できる可能性を秘めています。周囲の理解と正しい指導があれば、左利きの子が自信を持って音楽に向き合える環境は十分に整えられるはずです。
両利きの子はピアノでどう育つ?

両利きの子どもは、ピアノ学習において特に柔軟な対応力を発揮しやすい存在です。一般的に、ピアノ演奏では両手の動きが完全に独立していなければなりません。
その点、左右どちらの手にも偏りが少ない両利きの子どもは、自然な形でそのバランス感覚を習得しやすくなります。
多くのピアノ学習者は、非利き手の指の動きに時間をかけて慣れていく必要がありますが、両利きの子はその負担が比較的少ないといわれています。
たとえば、右手のスケール練習と同時に左手でも同じように練習を進めることが可能で、結果として効率よく技術が身についていく傾向があります。
また、両利きの子は指の独立性が高く、左右同時進行のフレーズやポリフォニーにも順応しやすいです。バッハのインベンションのような、両手で異なる旋律を奏でる作品に取り組んだ際にも、無理なく表現力を発揮することができるのが特徴です。
これは演奏面における大きなアドバンテージとなります。
ただし、注意点もあります。両利きの子どもは、その分「どちらを利き手として優位に使うか」が曖昧になりやすく、細かい動作においてどちらの手に力を入れるかが定まらないことがあります。
そのため、レッスンでは左右の役割を明確に伝え、どちらかの手に少しずつ精度を集中させるように導く必要があるでしょう。
教育者としても、両利きの子には柔軟性を活かしたカリキュラム設計が求められます。和音練習や分散和音など、両手を対等に使うメニューを取り入れると効果的です。
このように、両利きの子どもは、ピアノの習得においてバランス力や柔軟性を活かしやすい存在です。適切な指導を行えば、将来的には多彩な表現ができるピアニストへと育っていく可能性が高いといえるでしょう。
左利きのピアニストで有名な人

世界的に活躍している左利きのピアニストは意外と多く、その存在が「左利きでも十分にピアノを極められる」ことの証明となっています。彼らの演奏には独自のアプローチが感じられ、音楽的個性を際立たせる要因の一つとしても注目されています。
中でも有名なのが、坂本龍一さんです。日本を代表する音楽家であり、ピアニスト、作曲家としても国際的に高い評価を得ています。
坂本さんは左利きであることを公言しており、繊細で洗練された演奏スタイルは、左右のバランス感覚を活かした表現に富んでいます。映画音楽やソロピアノ作品など、幅広いジャンルでその才能を発揮しました。
もう一人、ロシアの作曲家でありピアニストでもあるセルゲイ・ラフマニノフも左利きであると伝えられています。
彼のピアノ協奏曲第2番や前奏曲などは、技術的な難易度が高いことで知られており、その演奏には極めて高い指の独立性とパワーが求められます。
左手の低音部の表現力が豊かである点においても、左利きの特性が演奏に良い影響を与えていたと考えられています。
また、クラシック以外のジャンルでも、ビル・エヴァンスやマッコイ・タイナーといったジャズ界の巨匠たちが左利きとして知られています。
彼らの演奏には、伝統にとらわれない自由なリズム感と、左右の手を駆使した即興性が強く表れており、左利きの柔軟な発想が音楽に良い形で現れているとも言えるでしょう。
さらに、クリストファー・シードというピアニストは、自身が左利きであることから、左右逆に設計された「左利き用ピアノ」を特注で製作しました。
このようなケースは非常に稀ですが、演奏スタイルに合わせて楽器そのものをカスタマイズするというアプローチは、左利きが音楽にどれほど情熱を注げるかを示す好例です。
これらの例からもわかる通り、左利きであることはピアニストにとって障壁にはなりません。それどころか、個性として音楽表現に反映されることもあり、聴衆に強い印象を与えることもあります。
左利きの子どもが将来に希望を持てるよう、こうしたピアニストたちの存在を伝えていくことも大切です。
左利きでピアノを楽しむための工夫

-
ピアノの才能がある人の特徴とは
-
4歳でピアノを始めるとどうなる?
-
音楽の聞こえ方に左右差はある?
-
左利き向けのピアノ曲を紹介
-
バイオリンやピアニカとの違い
-
ピアノは自由に楽しめる時代へ
ピアノの才能がある人の特徴とは
ピアノの才能とは、生まれ持った資質だけで決まるものではありません。一定の特徴を備えた人が、努力を重ねることで開花するものだと多くの指導者が語っています。では、どのような特徴が「才能のある人」に見られるのでしょうか。
まず、音に対する感受性の高さが挙げられます。これは単に「音がよく聞こえる」という意味ではなく、「音色の違い」や「微妙な強弱のニュアンス」を感じ取り、それを演奏に活かす力のことです。
たとえば同じ「ド」の音でも、鍵盤の押し方やペダルの使い方によって響き方が異なります。その違いを意識できる人は、音楽表現に深みを出せるようになります。
次に重要なのが、手指の独立性と柔軟性です。ピアノは10本の指を別々に動かす必要があり、特に薬指や小指を他の指と連動させずに使える人は、テクニック面での伸びが早い傾向にあります。これはトレーニングで向上する部分もありますが、元から器用な指の動きを持つ人は、複雑な楽曲でも無理なく対応しやすいです。
また、集中力と継続力も無視できません。短時間でも集中して練習できる子は、吸収力が高く、成長速度も早いです。
さらに、地道な練習を飽きずに続けられるかどうかも、長期的に見れば非常に大きな要素です。感性があっても、継続しなければ実力には結びつきません。
そしてもうひとつ、楽譜を見てすぐに音に変換できる「初見力」も大きな強みです。これは視覚的な情報を音に結びつける力で、特にアンサンブルや伴奏の場面で即戦力となります。子どものうちからこの力を育てていくと、音楽の世界での幅が一気に広がります。
このように「才能」と言われるものの正体は、いくつかの具体的な特徴に分解できます。どれか1つがずば抜けていても、他がついてこなければバランスは崩れます。だからこそ、総合的な力を少しずつ育てていくことが、結果的に「才能ある演奏者」への道をつくるのです。
4歳でピアノを始めるとどうなる?

4歳という年齢でピアノを始めることには、多くの可能性が秘められています。この時期は手先の器用さや感受性がぐんと発達するタイミングであり、音楽教育を取り入れるには最適な時期といえるでしょう。
まず、4歳はまだ利き手の機能が完全には固定されていないため、左右の手に極端な差がない子どもが多いです。
この段階でピアノを習い始めると、両手をバランスよく育てることができ、偏りのない演奏スキルを身につけやすくなります。将来的に難易度の高い曲を演奏するうえでも、この基盤が大きな強みになります。
また、この時期は耳の発達も著しいです。音の高低、リズム、音色の違いなどを敏感に感じ取りやすく、音感教育を始めるにはうってつけです。
実際、ソルフェージュやリトミックを併用したピアノ指導では、4歳児の吸収力の高さに驚かされることがよくあります。繰り返し音を聞いて模倣する力があるので、正しい音感とリズム感を自然に身につけられるのです。
ただし注意すべき点もあります。4歳は集中力が長く続かないことが多いため、レッスンは短時間かつ楽しめる工夫が必要です。「上達」よりも「音楽を好きになること」を重視する姿勢が、長く続けるうえでは欠かせません。先生や保護者の接し方によって、子どものやる気や自信にも大きく影響します。
さらに、この年齢でピアノを始めると、将来的に両手の協調性や身体全体のリズム感も育ちます。ピアノを通じて得られるこれらの力は、他のスポーツや学習にも良い影響を与えると言われています。
このように、4歳でのピアノスタートは、音楽的な基礎だけでなく、感性や身体の発達にも良い刺激をもたらす可能性があります。大切なのは、子どもが無理なく楽しめる環境を整えてあげることです。
音楽の聞こえ方に左右差はある?
人間の聴覚は、脳の左右で異なる処理をしていることが知られています。これにより、音楽の「聞こえ方」にも左右差が存在する可能性があると考えられています。特に、音の種類や聴取する目的によって、この差は顕著に表れることがあります。
たとえば、言語音は主に左脳で処理されます。一方、音楽の中でも旋律の美しさやリズム、ハーモニーといった非言語的な要素は、右脳がより深く関与すると言われています。
つまり、右脳の働きが活発な人は、音楽の情緒的な部分や細かなニュアンスに対して敏感に反応しやすい傾向にあるのです。
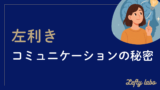
左利きの人は右脳が優位であることが多く、音楽の聴き方にも独自の感性が表れることがあります。実際、音の配置や重なり方に対して鋭い感覚を持ちやすく、複雑な和声や異なるパートのバランスを無意識に捉える力を発揮する人もいます。
これにより、演奏時のアンサンブル感覚や音色の選び方にも影響を与える場合があります。
一方で、訓練によってこの左右差はある程度調整されていきます。ピアノのように両耳・両手を均等に使う楽器では、音を「どちらの耳でどう聞いているか」という意識も徐々にバランスが取れてきます。
ですから、仮に初期段階で「音の偏り」を感じたとしても、継続的な演奏経験によってその差は薄れていくケースがほとんどです。
また、音楽の聞こえ方に差があるからといって、優劣があるわけではありません。ある人は旋律を中心に楽しみ、別の人はリズムに敏感に反応する。それぞれの聞こえ方が、その人ならではの音楽の感じ方や表現の個性につながっていくのです。
このように、脳の左右によって音楽の受け取り方に違いはあるものの、それはネガティブな要素ではありません。むしろ、音楽を多様に楽しむヒントとして前向きに捉えることができるでしょう。
左利き向けのピアノ曲を紹介
左利きの人がピアノを学ぶうえで、「左手にメロディがある曲」を積極的に練習することは、モチベーションの維持にも大きくつながります。
一般的なピアノ曲は右手に主旋律が割り当てられていることが多いため、左手が活躍する楽曲は貴重な存在です。ここでは、左利きの人にとって親しみやすく、かつ技術の向上にもつながるピアノ曲をいくつか紹介します。
まずはシューマンの「楽しき農夫」が挙げられます。これは比較的やさしい難易度で、左手がメロディを担うパートがあるため、左利きの初級者でも取り組みやすい一曲です。音楽的にも親しみやすく、達成感を得やすいため、初期のレッスンにぴったりです。
もうひとつおすすめなのが、同じくシューマンの『ユーゲントアルバム』に収録されている「勇敢な騎手」。この曲では、途中の中間部に左手でメロディを弾く場面があり、左利きの人が自然と音の出し方や力加減に意識を向ける練習になります。左右のバランス感覚を身につけるにも有効です。
また、クラシックだけでなく、現代的なアプローチとして左手の技巧を強化できる練習曲集もあります。たとえば、チェルニーの「左手のための練習曲」や、モシュコフスキーの「15の練習曲 Op.72」は、左手単独または左手中心に構成された内容で、左利きの演奏力向上に特化した教材と言えるでしょう。
近年では、左手の演奏に焦点を当てた独奏曲やアレンジも徐々に増えており、ネット上での配信も進んでいます。曲選びにおいては、ただ難易度だけでなく「左手が主役になれるかどうか」を基準にすると、より自然に演奏に入り込むことができるでしょう。
このように、左利き向けにおすすめできる曲は確かに存在します。演奏する喜びを実感しながら、左手の表現力を活かせる曲を意識的に取り入れることで、ピアノ学習がより自分らしいものになるはずです。
バイオリンやピアニカとの違い

ピアノとよく比較される楽器として、バイオリンやピアニカがあります。どれも子どもから大人まで広く親しまれている楽器ですが、演奏スタイルや身体の使い方には明確な違いがあります。
特に左利きの人にとっては、どの楽器が自分に合っているのかを理解するために、これらの違いを知ることは大切です。
まずバイオリンですが、基本的には左肩に構えて左手で弦を押さえ、右手で弓を使って音を出します。つまり、演奏の中で両手の役割が明確に分かれており、右利き前提の設計になっています。
左利きの人にとっては、右手での細かい弓のコントロールに苦戦することがあるかもしれません。ただし、世界には左利き用のバイオリンも存在しており、調整可能な面もあります。とはいえ、日本の教室では左利き用のバイオリンを取り扱っていないことが多く、対応には限りがあります。

次にピアニカですが、これは鍵盤ハーモニカとも呼ばれ、左手で楽器を支えながら右手で鍵盤を弾き、口で吹いて音を出します。この楽器も右手優位での演奏が前提となっているため、左利きの子どもにとっては「最初のつまずき」になることがあるかもしれません。また、ピアニカは音域が限られているため、ピアノのように自由度の高い表現を目指すには不向きです。

一方で、ピアノはというと、左右の手が常に連動して動く楽器であり、左手も右手も主役になれる可能性を持っています。もちろん右利き前提の楽譜は多いものの、学習を進めるうちに左右のバランスを鍛えることができるのが大きな特長です。手の使い方においても、固定的なパターンに縛られにくく、利き手に応じた柔軟な練習が可能です。
このように、バイオリンやピアニカは「利き手の影響を強く受ける設計」であるのに対して、ピアノは「両手を育てる前提」で成り立っているため、左利きでも順応しやすい傾向があります。自分の利き手や得意な動きを考慮して楽器選びをすることで、より自然に音楽を楽しめるようになります。
ピアノは自由に楽しめる時代へ
ピアノはかつて、「楽譜通りに正確に弾くこと」が最も重視されていた楽器の一つでした。しかし今では、演奏スタイルや学び方に多様性が生まれ、自由に楽しめる時代へと変化しつつあります。この変化は、左利きの人にとっても大きなチャンスと言えるでしょう。
まず、指導法の進化が挙げられます。これまでのピアノ教育では右利きを前提とした教材や教え方が主流でしたが、現在では両手をバランスよく使うことを重視したメソッドや、左利きの子どもにも対応可能な柔軟なレッスンが広がっています。
特に個人レッスンでは、講師が生徒一人ひとりに合わせた練習法を提案できるため、「どちらの手が利き手か」を問題視することは減ってきました。
さらに、テクノロジーの進歩によって、ピアノ学習の自由度が格段に上がっています。アプリやオンライン教材を使えば、自分のペースで学べる環境が整い、苦手な部分だけを重点的に練習することも可能です。また、自動演奏付きの電子ピアノなども登場し、音楽へのハードルが一気に下がりました。
演奏スタイルにも変化があります。クラシックだけでなく、ジャズやポップス、アレンジ演奏など、自分の感性を活かした自由なスタイルが受け入れられるようになってきました。左利きの人が得意な左手の動きを活かして、オリジナルな伴奏を作ったり、アレンジを加えることで、より自分らしい表現ができる時代です。
また、SNSやYouTubeを通じて、個人の演奏が世界に向けて発信できるようになったことも大きな追い風です。型にはまらない自由な演奏が評価される時代では、個性が最大の強みになります。つまり、左利きというだけで周囲と違う感覚を持つことが、かえって魅力として認識される場面が増えているのです。
今の時代、ピアノは「クラシックを正確に弾く」だけのものではありません。楽しみ方は人それぞれであり、左利きであることも、ひとつの音楽的な武器になります。誰もが自分のペースで、自分らしい音を奏でられる。まさに、ピアノは自由に楽しめる楽器へと進化しているのです。
左利きでピアノ演奏をするときの実態と学びの総まとめ
最後に、本記事のまとめとして箇条書きで総括していきます。左利きのピアノ演奏は、他の特徴的な楽器と比べそこまで気にする必要もないかもしれませんね。(ちなみに私は挫折しましたが・・)
-
左利きは右利き社会で不便を感じやすい側面がある
-
ピアノは基本的に右手主導の楽譜構成が多い
-
左利きの人でもピアノ演奏は十分に可能である
-
左手の器用さが低音や伴奏で強みになる
-
左利きのピアニストも世界で高く評価されている
-
左右バランスを重視した練習が上達のカギとなる
-
左利き向けに左手主体のピアノ曲も存在する
-
幼少期からの習得で左右の手をバランス良く育てられる
-
両利きの子どもは演奏の柔軟性と応用力が高い傾向にある
-
音楽の聞こえ方に左右差があり感性の違いが出やすい
-
バイオリンやピアニカは右利き前提の設計が多い
-
ピアノは両手を均等に使うため左利きにも向いている
-
現代はピアノの楽しみ方が多様化している
-
アプリやオンライン教材で個別最適な学習が可能
-
ピアノは個性を活かして自由に演奏できる時代になった


